![]()
死にたくなる薬
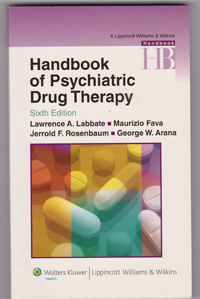 (注)斎藤友紀雄 斎藤友紀雄は精神科医でも医師でもありません。東京神学大学とアメリカの神学校で神学と臨床心理学を学んだ、日本キリスト教団の牧師です。 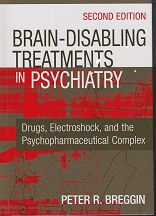 |
中枢神経抑制剤 中枢神経抑制剤と分類される薬があります。文字通り脳や脊髄にある中枢神経の働きえを抑える効果を持つ薬です。英語ではCNS depressant (CNS=Central Nervous System)と呼んでいます。短く、ダウナー(downer)と呼ぶこともあります。一番身近な中枢神経抑制剤はアルコールです。お酒を飲み過ぎると現れる典型的な症状、千鳥足、舌のもつれた話し方等は皆アルコールの影響で中枢神経が抑制されてしまった結果です。アルコール中毒者に自殺が多いのは、アルコールの中枢神経抑制作用の結果、気分や感情も落ち込んでしまって、抑うつ症状(depression)に至るからです。またアルコール中毒症の治療のために医師から投与された精神薬の影響も考えられます。厚生労働省が平成24年2月に発表した「病院・診療所における向精神薬取扱いの手引き」の5頁以降にある「向精神薬一覧」を見ると、ベンゾジアゼピン系薬剤は軒並み薬理作用は「中枢抑制」と分類されています。「中枢神経抑制剤」であるということです。ここでいう「向精神薬」は「麻薬及び向精神薬取締法」で規定した狭義の「向精神薬」ですが、広義では抗精神病薬や抗うつ薬等の精神治療薬は皆、「向精神薬」に入ります。 統合失調症の薬である抗精神病薬(antipsychotics)も中枢神経抑制剤です。 ドーパミン等の神経伝達物質の働きを弱めることによって、中枢神経の興奮を抑え、鎮静化させる効果があります。真実7の検証の節で述べたことですが、イギリスのウエールズ大学の精神科教授、デイビッド・ヒーリーが抗精神病薬第一号のクロルプロマジンが発明される前のウェールズの精神科病院の統合失調症患者の自殺率は通常の健康人の場合と同じでしたが、クロルプロマジン等の抗精神病薬が使われる時代になると、自殺率はその20倍に激増したということでした。抗精神病薬という中枢神経抑制剤を服用することで、患者の抑うつ(depression)が強まったのです。それが患者の自殺につながっているのです。 ベンゾジアゼピンが開発される前に睡眠薬や抗不安薬としてよく使われていたバルビツール酸系薬剤(barbiturate)も中枢神経抑制剤です。ベンゾジアゼピンと同じように、バルビツールにもいくつもの種類があります。よく知られたものでは、バルビタール(barbital)、アモバルビタール(amobarbital)、フェノバルビタール(phenobarbital)などがあります。麻酔薬や抗てんかん薬として使われることもあるようです。バルビツール酸系薬剤は依存や耐性がつきやすく、かつ過量にとった場合には、死に至ることが問題となりました。ベンゾジアゼピンのまだなかった時代に、日本の作家の芥川龍之介やアメリカの女優のマリリン・モンローが自殺する時に使った薬はバルビツール酸系睡眠薬でした。バルビツールは致死性が高いので危険であると思われていますが、それよりももっと根本的に問題なのは、強力な中枢神経抑制剤であるが故に服用者に抑うつや希死念慮が生まれるということです。依存と耐性によって服用量が徐々に増えて行きますが、それに伴なって、死にたいと思う気持ちが強まって行くのです。 それまで使われていたバルビツールに代わるものとして登場したのがベンゾジアゼピンです。ホフマン・ラロシュ(Hoffmann-La Roche)が1950年末から1960年初期にかけて、クロルジアゼポキシド(chlordiazepoxide)やジアゼパム(diazepam)といったベンゾジアゼピン系薬剤を開発・製造・販売し、その後他社もベンゾジアゼピン系薬剤を手掛けるようになりました。バルビツール程に依存性も致死性も強くはなく、安全な薬剤であるというロシュを初めとする製薬会社のプロモーション効果が働き、ベンゾジアゼピンはバルビツールに代わるものとして市場を席巻しました。ベンゾジアゼピンが初めて世に出てからもう50年以上経つのですが、未だに「最近の睡眠薬は昔のものと比べると安全です」と患者に言ったり、書物に書いている医師がいるのです。ベンゾになってバルビツールと比べると確かに致死性は弱まったと言えますが、中枢神経抑制作用はベンゾでも変わらないのです。抑うつをもたらすという作用は依然としてベンゾでも残るのです。 そろそろベンゾジアゼピンもそれ程安全な薬ではないことが世間で判ってきました。このサイトを注意深く読めば、その理由を理解頂けるでしょう。 中枢神経を抑制すれば、例えば心臓の動きとか肺の動きをコントロールしている自律神経の働きを抑制することになりますから、抑制が強ければ心臓が止まったり、肺の呼吸が停止するといった事態が起こり、死に至ります。バルビツールが危険な薬である理由です。 しかし中枢神経抑制剤の怖さは、自律神経の働きに影響を与えて、身体を正常にコントロールできなくするということに留まりません。人間の精神の働きや感情の動きも中枢神経によって律せられています。中枢神経抑制剤を使えば身体の働きのみならず、精神や感情の働きにも影響が出てきます。そもそもそれを狙って精神治療薬が使われるわけですが、精神や感情への影響がすべてよいものであるとは限りません。往々にして好ましくない影響が出てしまうことが多いのです。 中枢神経抑制剤は英語ではCNS depressantであると既に申し上げました。抗うつ薬のことを英語ではantidepressantと呼びます。抑うつもうつ病も英語ではdepressionです。中枢神経抑制剤を使えば、身体の働きを自律的に司る中枢神経を抑制するだけではなく、心の働きも抑制する(depressする)ことになります。つまり抑うつ感、抑うつ気分、抑うつ症状が高まることになるのです。ベンゾジアゼピン系薬剤も中枢神経抑制剤ですから、ベンゾジアゼピン服用者に抑うつ、症状が現れるのです。特に長期に渡って、大量に飲めば抑うつ症状が強く現れます。死にたいとか、この世から消え去りたいといった希死念慮がその結果出てきます。困ったことには、服用者自身が死にたくなったのは薬の影響でそうなったと気が付かないことが多いということです。本人が気が付かないくらいですから、薬を処方した医師も、真実1と真実2が適用され、薬のせいで患者が死にたいという気持ちを抱くようになったと気が付いていないのです。抑うつになったり、死にたくなったのは、元からあった抑うつや、うつ病のせいであると自分に都合の良い解釈をしてしまうのです。 アメリカで発行された本でHandbook of Psychiatric Drug Therapy(精神科薬剤療法ハンドブック)という題名の本があります。4人の共同執筆者が書いた本で、4人の内の二人がハーバード大学医学部精神科の教授で、二人共ハーバード大学医学部の附属病院であるマサチューセッツ総合病院(Massachusetts General Hospital)で勤務している医師、残りの二人はそれぞれアーカンソー大学とバンダービルト大学の医学部精神科の教授です。皆一流大学の医学部教授であり、それなりの社会的信用もあるはずです。第6判まで出ていて、小型で軽い本なので、ポケットに忍ばせて持ち運ぶのに便利なこともあって、アメリカの精神科医が参照してよく使っている本と思われます。この本の第5章 不安障害の治療のための薬(Drugs for the Treatment of Anxiety Disorders)に以下の記述があります。 「ベンゾジアゼピン誘発性抑うつ. すべてのベンゾジアゼピンが抑うつの出現または抑うつの悪化に結び付けられてきた。抑うつの原因になっているのか、抑うつを単に予防できなかっただけなのかは不明である。治療の途中で抑うつが発生した場合には、ベンゾジアゼピンに抗うつ薬を加えるか、あるいはベンゾジアゼピンの代わりに抗うつ薬を使うことができる。」 "Benzodiazepine-Induced Depression. All benzodiazepines have been associated with the emergence or worsening of depression; whether they were causative or only failed to prevent the depression is unknown. If the depression occurs during the course of treatment, the benzodiazepine can be combined with or replaced by an antidepressant." 「抑うつの原因になっているのか、抑うつを単に予防できなかっただけなのかは不明である」と書いてありますが、これも常套手段としてよく使われる精神科医の弁明です。薬によって何か精神症状における副作用が出た場合には、それを病気そのもの、精神疾患そのもののせいにしてしまうというやり方です。もともと抑うつ(うつ病)になるような人だったので、ベンゾジアゼピンを使ってもそれを防止できなかったのだという主張です。日本の場合は特に極端ですが、精神科医は日本でもアメリカでもヨーロッパでも同じです。自分たちの職業は処方箋薬を患者に投与できるという政府が与えてくれた特権の上に成り立っています。薬を処方できなくなったらお手上げです。彼らの職業の存亡がかかっています。ですから薬の悪口は言いません。薬の副作用で何か有害症状が現れても、それが特に精神症状における有害症状の場合には、それは薬に原因があるとは認めません。真実1と真実2(あるいはその裏の間違った思い込み1と2)があるがゆえに、何をいっても世の中ではそれで通ってしまうのです。 EU(欧州連合)のベンゾジアゼピンの医薬品添付文書のガイドライン(英語)(日本語)を再び読んで見ます。以下のように書いてあります。 「抑うつ(うつ病)や抑うつ(うつ病)に伴う不安症状の治療にベンゾジアゼピンだけを使うべきではない(そういった患者では自殺が誘発されるかも知れない)」 "Benzodiazepine should not be used alone to treat depression or anxiety
associated with depression(suicide may be precipitated in such patients).” oxazepam may be less likely to trigger this effect. Many clinicians feel that the highest incidence of disinhibition occurs in personality disorder patients with prior histories of dyscontrol. When paradoxical excitemment occurs in a patient given a benzodiazepine in an emergency department or inpatient ward , the administration of an antipsychotic drug is often effective in reversing the state" . ここで注目すべきは「最も脱抑制が起こり易いのは人格障害の患者」というくだりです。真実1の検証の「精神科の診断」で明らかにしたように、精神科医にわかるのは患者の表に現れた行動だけであって、患者の心の中の状態は精神科医はあずかり知らないのです。怒りっぽい人、すぐ激怒したりしする人を見れば、精神科医はそれを人格障害と診断名を付けます。何かいらいらするような因子があると、それにすぐ反応して怒りを露わにするタイプの人と、それとは対極的に、自分の気持ちをこらえて表に出さない性格の人とがあります。ベンゾを服用して心の中ではイライラしても、それをこらえて、うまく自己コントロールして、自己抑制して表にイライラを出さない人の場合には、ベンゾ服用から来るイライラ因子が患者の心の中にあっても、精神科医それを見抜けないのです。そのために自らの心の中のイライラ因子に応じて怒りを表にぶちまける人、つまり人格障害と呼ぶ人に逆説的反応が多いと錯覚してしまうのです。救急の場とか入院病棟とかで、誰の目からみても明白な怒りの発露のみが逆説的反応であると思い込んでいるのです。 ところが統合失調症等の精神障害者に投与するとどのくらいの頻度で刺激、錯乱(逆説的反応)が起きるかの研究・調査は何もありません。(頻度不明)と書いてあることからもそれが判ります。根拠なく、エビデンスもなくこんなことを添付文書で言っているのです。精神治療薬、向精神薬によって、精神症状に有害な副作用が出た場合、それを精神疾患のせいにして、薬に原因はないとする主張は製薬会社や精神科医の常套手段です。 アメリカではAtivanという商品名で一般名lorazepamのベンゾが販売されていますが、Ativanの添付文書には逆説的反応について以下のように書かれています。 「ベンゾジアゼピンを使用中に逆説的反応が現れたとする報告が時折ある。そういった反応は "Paradoxical reactionshave been occasionally reported during benzodiazepine use. Such reactions may be more likely to occur in children and the elderly. Should these occur, use of the drug should be discontinued." 財団法人・生命保険文化センターが発行しているオンライン・マガジン「くらしと保険」に2007年9月に掲載されたある記事があります。「日本いのちの電話連盟」常務理事の斎藤友紀雄をインタービューした記事です。その記事の中で斎藤友紀雄が語るところによると、死にたくなって、つまり希死念慮が強まり、怖くなって助けを求めて「いのちの電話」に電話をかけてくる人のおよそ8割は精神科の受診歴があり、自殺未遂者の7割は電話をかけてきた時点で精神科を受診中で、投薬を受けているという事です。斉藤は「自殺者の8~9割はうつ病を抱えているといわれています」とも述べています。精神科を受診しているということはイコール精神治療薬を服用しているということに絶えず思いを致すべきです。。 「くらしと保険」 2007年9月 斎藤友紀雄のインタビュー ライフリンクの行った自殺実態調査に応じてくれたのは自殺者の遺族で、全国に散らばっており、東京からライフリンクの調査員が来て平均2時間半~3時間の面接をする事に同意してくれた事例ばかりです。なかなか同意してくれる遺族を見つけるのに苦労があったようで、当初1,000人の自殺者の遺族の聞き取り調査をするとして2007年7月に始めた調査ですが、最終的には自殺者523人分のデータしか集まっていません。しかも10年以上も前の自殺者の遺族から集めたデータもかなり混じっています。個人情報保護、プライバシーの問題があって、自殺者を見つけ出し、特定することも困難な作業と思われます。従ってライフリンクのデータには統計学的なランダム性は欠如しています。どうやって調査対象の自殺者を見つけ出したのか、サンプリングの手順をどう進めたのかについてのライフリンクの説明は何もありません。透明性が欠如しています。 「全国自死遺族連絡会」の調査 「全国自死遺族連絡会」というNPO団体があります。息子を自殺で失くした田中幸子という女性が中心になって自殺者遺族の支援活動を行っています。ライフリンクの場合には自殺者遺族でメンバーになっている人は極めて少ないのですが、「全国自死遺族連絡会」の場合にはメンバーは全員自殺者遺族です。前項で取り上げたライフリンクの調査で面接調査に応じてくれた自殺者遺族の多くが「全国自死遺族連絡会」がライフリンクに紹介した人達であるようです。「全国自死遺族連絡会」の調査では田中幸子代表世話人や彼女の仲間達が遺族と直接接触して、情報を集めています。 2010年4月7日に国会議員に自殺の問題を理解してもらうために、衆議院議員会館で勉強会を開き、代表世話人田中幸子が自分たちの調査で判った事を発表しました。その時に田中が勉強会参加者に配布した資料のコピーをご紹介します。また「全国自死遺族連絡会」の調査結果や活動について報じた地方紙の河北新報と読売新聞の記事を参考までに添えておきます。 ライフリンクの調査は523名の自殺者遺族の聞き取り調査でしたが、この「全国自死遺族連絡会」の調査の場合には1,016人の自殺者遺族と、母集団がより大きく、田中幸子代表世話役や彼女の仲間が遺族と親密にやりとりして聞き出した情報ですので、実態をよりよく反映しており、統計上のサンプルとしては信頼性が高いと思われます。 この資料では全平均で自殺者の約7割が生前に精神科を受診していたと指摘されています。また20代、30代、40代、50代の女性自殺者は100%全員精神科を受診していました。自宅マンションからの飛び降りによる自殺者72名が「全員」精神科の診療を受け、1回の服用5錠~7錠、1日3回、他寝る前に頓服、睡眠導入剤を服用していたとの事です。自宅、自宅近辺での自死は精神科の受診率が高いともこの配布資料には書いてあります。
2008年(平成20年)8月29日、、朝日新聞朝刊の読者投書欄「私の視点」に、ある精神科医の投書が載りました。日本の年間自殺者数が3万人を超える状態が何年も続き、メディアでもそれに注目して盛んに報道していた時期です。
この精神科医は20年間で自分の診ていた患者の内、56人が自殺したということです。一年間の自殺者は平均2.8人となります。驚くべき数字ですが、よく考えてみれば、当然そうなる筈の数字なのです。 ピーター・ブレギンの場合 真実6の検証の節で紹介したアメリカの精神科医の言った言葉を再びここで振り返って見ましょう。彼は病院勤めではなく、ニューヨーク州イサカ市に自らのクリニックを持つ開業精神科医です。40年間開業していて、自分の患者に自殺者を出したことは一度もないと彼は言っています。20年で56人の自殺者を出した日本の精神科医と、40年で自殺者ゼロのブレギンとは余りにも対照的です。どこに違いがあるのでしょうか。薬の処方であることは明らかです。ブレギンはこう書いています。 「これは何度繰り返して言ってもいい。抗うつ薬は効果がないだけではなく、抗うつ薬の服用を始めることも、抗うつ薬を止めることも危険なことである。最良の忠告は抗うつ薬には手を出すなということである。私は40年間に及ぶ精神科臨床で、離脱過程の患者が離脱をうまく進められない時に抗うつ薬を処方することはあっても、患者に抗うつ薬を開始させたことは一度もない。確かに幸運も疑いなく働いていたと思うが、私が患者にこれらの薬を開始させないということが、私の臨床では自殺者を一人も出していないという成功に与かっていると私は信じている。薬を出さないことで、抗うつ薬の誘発する自殺を予防することになるが、加えて、一緒になって、より効果的で希望あふれる生き方を見つけようと自分にも患者にも激励している。」
上述のライフリンク代表の清水康之が自殺について語り合うあるシンポジウムでこんな事を言っていました。ライフリンクというと、死にたくなったり、自殺したくなったりした時に相談に乗ってもらえる所、カウンセリングの場だと思って時々電話がかかってくることがあるようです。(実際は「いのちの電話」と違ってカウンセリングはやっていません。) ある時、そういった電話をかけて来た人に、それでは精神科にでも行ったらどうですかと助言すると、その電話をかけて来た人はこう言ったそうです。 |